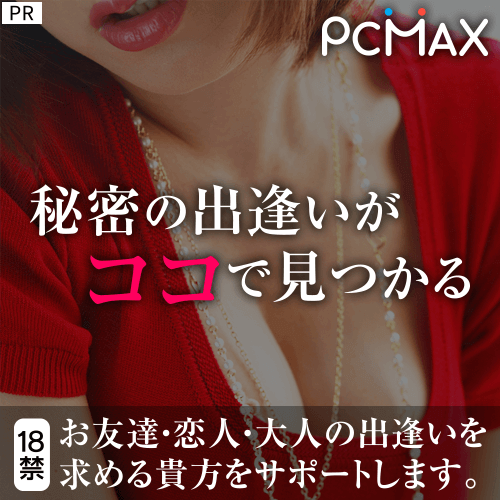「欲しいのは、恋じゃない。体温と、背徳感。」
そんな気持ちを抱くようになったのは、いつからだったろうか。
仕事に追われ、毎日が繰り返しのような生活。家と会社を往復するだけの毎日に、潤いなんてあるはずもなく、ふと目に入った出会い系アプリの広告を指でタップしていた。
俺が最初に登録したのは《PCMAX》。
世間で言われているような「サクラばかり」という印象は最初こそ強かったが、数日使ってみると、意外と“本物”が混ざっていることに気づく。
プロフィールを整え、いくつかの掲示板――ヤリモク掲示板、セフレ掲示板、援助交際掲示板などを巡っていくうちに、ある投稿が目に止まった。
「巨乳JD(19)♡今夜、横浜で会える人限定♡」
添えられた写真には、ショートカットのボーイッシュな雰囲気の少女が映っていた。切れ長の目元、どこか有名人に似た端正な顔立ち。そして、自己紹介文にはこう書かれていた。
「Aカップって信じられないかもだけど、形と感度は保証付き♡」
矛盾してるようで、なぜか妙にそそる。俺の好奇心はすでにMAXに達していた。
すぐにメッセージを送ると、わずか10分ほどで返事が返ってきた。
「今夜、関内で会える?ホテル代だけお願い♡」
どこか慣れている文面だったが、警戒心よりも興奮が勝った。何より、彼女のプロフィールには“エッチしたい”という直球の欲望が書かれていた。
名前はユウナ。19歳の現役女子大生、しかもシングルマザーだという。
彼女は、10代で妊娠し出産。現在は子どもを実家の祖母に預けながら大学へ通っているとのこと。
「ま、バツイチみたいなもんだよね」
と笑う彼女に、俺は一気に惹かれていった。
待ち合わせは、関内駅のロータリー。
夜8時、春の雨がぱらつく中、指定された場所へ向かうと、傘を差した小柄な女性がこちらに手を振ってきた。ショートカットにミニスカート、脚はすらりと長く、ダウンジャケットの中からは、豊満な胸のラインがはっきりと浮かび上がっていた。
「はじめまして、ユウナです」
その一言で、すべてが始まった。
彼女は軽快に話しながら俺の腕に自分の手を絡ませた。
「今日は筆おろしじゃないんだよね?最近そういう依頼ばっかでさ」
俺が童貞に見えたらしい。
「安心してくれ、俺は中年の独身リーマンだ」
そう答えると、彼女はくすっと笑った。
ホテルへ入るまでの道中、彼女は実に饒舌だった。
出会い系歴はすでに2年。ハピメ、ワクワクメール、Jメール、イククル、華の会メール、ASOBO…あらゆるアプリを使いこなし、「欲望」と「快楽」を味わってきたと話す。
「彼氏欲しい時期もあったけど、今は恋活より性癖合う人探してるかな」
ユウナの性癖は多岐にわたる。ロリコン、足フェチ、尻フェチ、うなじフェチ、視姦、露出、SM、アブノーマル、熟女好き、そして変態そのものを愛するという。
ホテルの部屋に入ると、彼女はさっそくカバンから道具を取り出し始めた。
電マ、ローター、バイブ、バイブレーター、吸引グッズ、メシベ型ディルド、大人のおもちゃ、スカイビーンズ…。
「今日は“ドMのユウナ”ってことでよろしくね♡」
俺がシャワーを浴び終えると、彼女はすでにベッドの上で素肌を晒し、四つん這いになっていた。
プレイはまさに濃厚だった。
まずは手コキ、フェラ、フェラチオから始まり、クンニで何度も絶頂を迎えた彼女は「中にちょうだい」と囁いた。
迷いもなく、俺はゴムをつけずにそのまま中へ挿入した。
ユウナの中は信じられないほど熱く、そして締まりが強く、まるで俺の欲望を受け止めてくれるかのようだった。
1回、2回、3回…彼女の喘ぎ声が部屋中に響くたび、俺の理性はどんどん壊れていった。
「アナルも、試してみたい?」
その一言で俺は、人生初のアナルセックスを経験した。彼女は痛がる素振りもなく、むしろ快感を求めて腰を振った。
バイブを使いながらの同時責めで、彼女は何度も潮を吹いた。
気がつけば朝になっていた。
ベッドの上には、ぐったりとしたユウナ。
「久しぶりに、本気で気持ちよかった」
そう言って、俺の腕を枕にして眠る彼女の表情は、とても19歳とは思えないほど成熟していた。
帰り際、彼女はこう言った。
「また、ヤリモク掲示板に投稿すると思うから、見かけたらメッセしてね」
その言葉が、妙に寂しげに聞こえた。
俺はその日以来、ますます出会い系の沼にハマっていった。
人妻、OL、看護師、AV女優、主婦、キャバ嬢…。
三宮、天王寺、京橋、鶴橋、新大阪──
大阪や横浜だけでなく、地方都市でも次々と体験を重ねていった。
けれど、あの夜のユウナほど、心も体も燃やされた相手はいない。
彼女のように、強く、自由に、欲望に忠実な女は希少だ。
俺は今でも、出会い系アプリを開くたびに、彼女の名前を検索してしまう。
いつかまた、関内のロータリーで手を振る彼女に、再び会えることを願いながら──。