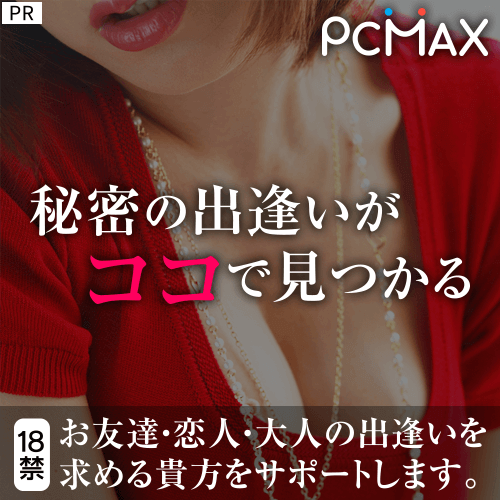雨の夜に交差する鼓動|人妻と出会い系の仮面
――雨の匂いが、欲望を濡らす夜がある。
深夜1時をまわった頃、僕はいつものようにPCMAXの「人妻掲示板」を眺めていた。アルコールと自慰だけでは埋まらない空虚を抱えたまま、誰かの嘘でも優しさでもいいから、この不毛な孤独に差し込む灯が欲しかった。
フリーライターという職業は、自由と引き換えに常に孤独を背負う。打ち合わせもない日など、誰とも言葉を交わさずに日が沈む。そして気がつけば、歳だけが重なり、セックスからも愛からも遠ざかっていた。
「人妻」「セックスレス」「羞恥」「バイブ使用可」――
そんなタグに引かれるようになったのは、ちょうど30歳を過ぎてからだった。恋愛感情のない快楽。家庭という聖域を抜け出し、抑圧された欲望を曝け出す人妻との交わり。それが僕の中で、純粋な恋愛以上にリアルで、淫靡で、美しいものに思えた。
◆人妻・瑠美(るみ)との出会い
「今から会える方限定/港区・既婚37歳/ホテル代出します」
そんな掲示板の一文が、目に刺さった。投稿したのは「Rumi37」。文章はそっけないが、どこかに滲む切実さがあった。アイコンも顔出しなし。だが、それが逆に本物感を際立たせていた。
― どうせ、冷やかしや業者か、すぐLINE誘導してくる人だろう。
そんな半ば冷笑的な気持ちで、「こんばんは、今からお会いできますか?」とだけメッセージを送った。すると、5分と経たないうちに、返信が来た。
Rumi37:
ご連絡ありがとうございます。今、品川の東横INN近くにいます。今夜は、夫が夜勤で不在でして…。
まさかの即レス。しかも、かなり具体的な場所指定だ。
Rumi37:
セックスレスで、ずっと女性として扱われていません。誰かに、女として見られたくて。
その一言で、僕の心は不意打ちを受けたように揺れた。
◆人妻という仮面、その下の素顔
15分後、僕は傘を片手に品川駅前のロータリーに立っていた。ずぶ濡れのネオンが歩道に反射し、そこに、ひときわ背筋の伸びた女性が立っていた。黒のトレンチコートに包まれた長身、真っ直ぐな視線。思ったよりずっと綺麗だった。
「…新海さん、ですか?」
「はい。瑠美さん…?」
夜の雨音が、会話を濡らしていた。彼女の声は落ち着いていて、どこか眠るように柔らかかった。
近くのカフェで少し話しませんか?と僕が言うと、彼女は小さく頷いた。
◆カフェで明かされた瑠美の秘密
カフェラテを前に、彼女は自分のことを語り始めた。
-
結婚して10年。子供はいない。
-
夫は歯科技工士で、夜勤も多く、セックスは4年以上ない。
-
最初は「私が女としての魅力を失ったのだ」と思った。
-
でも、職場では「色っぽい」と言われることもあった。
「…女って、誰かに“抱かれたい”って思われて初めて、自分の存在を肯定できるんだと思うんです」
その言葉を聞いたとき、僕はただ静かに頷いた。彼女の瞳の奥に宿る寂しさは、僕のものと似ていた。
「お願いがあります」と、彼女が言った。
「ホテルで、何も言わずに私を脱がせてほしい。自分から求めたくないんです。…“連れてこられた”ようにしたい」
それは、羞恥と服従、そして人妻の背徳をすべて内包した願いだった。
◆ホテルまでの無言の移動
カフェを出ると、雨は弱まっていた。彼女は無言で、僕の2歩後ろをついてきた。まるで、意識的に「連れてこられている演出」をしているようだった。
品川駅近くのラブホテル街。ビジネスホテル風の一室に入り、僕はそっとバッグを開けた。
― アダルトグッズも持ってきている。彼女の希望に応えるために。
ローター、軽めのバイブ、手枷、アイマスク…。どれも派手ではなく、だが彼女の「被虐願望」には応えられるものだった。
ベッドに座らせた彼女は、コートの下にベージュのワンピースを着ていた。ゆっくりと、その背後にまわり、ファスナーを下ろす。何も言わずに。
背中が露わになり、白い肌にほくろが一つ。下着は黒のレースで、予想以上に大胆だった。
「…脱がされるって、恥ずかしいですね」
ようやく漏れたその一言に、僕の理性は静かに切れていった。
第2部:雨音に沈む喘ぎ声|抑圧と快楽の境界線
――黒いレースのブラを指先で外したとき、彼女の肩がほんのわずかに震えた。
ベッドに腰掛けたまま、僕を見上げる瑠美の視線には、羞恥と期待、そしてほんの微かな恐れが宿っていた。37歳という年齢をまったく感じさせない肌の艶。その首筋から鎖骨にかけて、雨に濡れたような光沢が浮かんでいた。
「……こうして見られるの、慣れてないんです」
ぽつりと呟いた彼女の声は、まるで深夜ラジオのように、静かに僕の鼓膜を撫でてきた。
「じゃあ、慣れさせてあげましょうか。たっぷりと。」
囁くように言いながら、僕は鞄から取り出したローターを手のひらで温めた。それはごくシンプルなタイプで、白いコードの先に楕円の振動子がついている。
「瑠美さん、今日は“自分を取り戻す夜”にしませんか?」
そう言って、そっと彼女の太腿にローターをあてた。
電源を入れると、微かな振動音が静かな室内に響く。彼女の身体がびくっと震え、頬が赤く染まった。
「や……だめ、そこ……」
拒絶にも似た声。しかし、腰は逃げず、むしろ僕の手を迎え入れているようだった。
ワンピースの裾を捲り上げ、ショーツの上からローターを押し当てると、彼女の呼吸が浅くなった。熱を帯びていく布越しに、彼女の体温と欲望がダイレクトに伝わってくる。
「ほら、もうこんなに濡れてる」
「……やだ、言わないで」
羞恥に身を震わせながらも、ローターの振動を拒めない。人妻という仮面が剥がれかけていた。
◆背徳に染まる白い肌
アイマスクを手に取ると、彼女はほんの一瞬だけためらいの表情を見せた。
「見えないと、余計に感じてしまうんです」
「それが狙いですよ」
僕はアイマスクを優しく彼女の目元に添え、そっと装着した。その瞬間、彼女は視覚を奪われ、聴覚と触覚が研ぎ澄まされていく。
「じゃあ、今から全部“僕に任せる”ということで」
彼女は小さく頷いた。口では言葉を発しないが、その全身から伝わってくる“委ねる覚悟”が、僕の興奮を煽った。
手枷を装着し、ベッドのヘッドボードに固定。両手を縛られた瑠美は、まるで生け贄のように無防備だった。なのに、その表情には苦しみよりも、安堵が浮かんでいるように見えた。
「……女って、支配されることで安心すること、あるんですよね」
ふと漏れたその一言が、どこか物悲しくて、切なかった。
◆バイブの鼓動と、雨のリズム
「準備はいいですか?」
「……はい」
小さな声と同時に、僕は黒いバイブを挿入した。まだ浅い段階で、彼女の腰が大きく跳ねた。
「や、あっ……奥は……だめ……っ」
それでも、彼女は逃げようとはしなかった。むしろ、自ら腰を押しつけてくるような動きさえ見せていた。
「こうされるの、ずっと、ずっと、夢だったんです……」
快楽と羞恥が入り混じった声。アイマスクの下で潤む目元が、バイブの振動と共にわずかに震えていた。
そのまま速度を変えながら、何度も彼女を攻め立てる。雨音が窓を叩く音に、喘ぎ声が混じる。
それはまるで、都会の片隅で交わされる密やかな儀式だった。
◆“人妻”という役割の崩壊
彼女の中で何かが崩れていく音が、聞こえた気がした。
ずっと主婦として、妻として、社会人として、真面目に生きてきた。その仮面が今、男に脱がされ、縛られ、バイブで揺さぶられている中で、音を立てて剥がれ落ちていく。
「……私、こんなに乱れる女じゃないのに……」
「本当のあなたは、こっちだったんでしょう?」
僕の問いに、彼女は何も言わず、ただ首を縦に振った。
――いや、違う。首ではなく、腰を。
自分から腰を突き上げ、快楽を求めている姿。それこそが彼女の“本当”なのだと、全身で語っていた。
◆解放と再会の余韻
1時間ほどでプレイは終わった。
手枷を外し、アイマスクを外した彼女は、少し涙を滲ませていた。
「……怖かったけど、終わってほしくなかった」
その一言が、僕の胸を締めつけた。
“抱かれたかった”のではなく、“女として扱われたかった”。
単なる肉体の交わりではなく、役割や日常を脱ぎ捨てた上での、尊厳の回復。それが彼女にとって、今夜の意味だったのだ。
服を整え、ホテルを出ると、雨は止んでいた。
「…また、会えますか?」
彼女がそう聞いたとき、僕はうなずく以外の選択肢を持たなかった。
「もちろん。また、連れてきますよ。あなたの“本当”を」
LINEの通知音が鳴る。そこには彼女からのメッセージ。
瑠美:
今日はありがとうございました。
久しぶりに“人間”に戻れた気がします。
その言葉が、僕の中でずっと消えなかった。
ホテルの扉が閉まったあと──人妻との背徳的な夜のはじまり
あの瞬間の緊張感は、今でも脳裏に焼き付いている。
ホテルの自動ドアが「ピッ」と音を立てて閉まり、受付の女性が事務的にルームキーを差し出したとき、彼女──「志保さん」は一瞬だけ躊躇したように見えた。
「……本当に、いいの?」
その問いに、俺はただ頷くことしかできなかった。
すでに背徳のスイッチは、どちらの心にも入っていた。
志保さんは41歳の人妻。
夫とは10年以上の結婚生活の末、完全なセックスレス状態。
「月に一度すらないの。もう、触れられることもない」
そう呟いた彼女の目は、どこか諦めと期待が混じったような色をしていた。
俺たちはPCMAXで知り合った。
掲示板ジャンルは「今から会いたい」。
その中でも一際目を引く投稿──
「誰にも言えない夜、ひとりで耐えている人妻です」
年齢、容姿、内容、すべてが俺のフェチを刺激していた。
やり取りは驚くほどスムーズだった。
LINE交換もすぐにできたし、「まずはお茶から」というお約束もなく、「車で拾ってもらって、ホテルで話せたら」と彼女から言ってきた。
「どうせ、このまま帰っても誰も何も聞かないから」
そう笑ったLINEスタンプのあとに、「お風呂入って待っててくれたら、うれしいな」と追撃が来たとき、俺の中の理性は音を立てて崩れた。
──ホテルの一室。
志保さんは、驚くほど丁寧に服を脱いだ。
「見られてると、緊張しちゃう」なんて言いながらも、その手つきは明らかに慣れていた。
ブラはCカップ。決して爆乳ではないが、形が整っていて、乳首が色っぽく、吸い付きたくなるようなピンク色だった。
「こんな風にじっくり見られるの、久しぶり」
そう言った声が少しだけ震えていたのは、恥ずかしさか、それとも欲情か。
俺は、何も言わずに彼女をベッドに押し倒した。
そして、ゆっくりと、長いキスをした。
舌を絡め合いながら、互いの手が体を探る。
彼女の指先が俺のズボンのチャックに触れたとき、思わず息が漏れた。
「……もう、したい?」
「したいです」
「ゴム、ある?」
「もちろん」
「えらいね」
そのやり取りが、妙に生々しくて、俺たちは一瞬だけ笑った。
そしてその笑いが、緊張をすべてほどいてくれた。
ベッドの上で彼女は、想像以上に淫らだった。
声も大きく、喘ぎ方もエロくて、体をくねらせながら何度も「もっと、もっと」とねだった。
「おち○ちん、奥まで……入れて……」
「気持ちいい……こんなに濡れるなんて……」
彼女のアソコは、人妻とは思えないほどきゅっと締まり、しかもとろとろに濡れていた。
バックで突きながら、俺は髪をつかみ、腰を深く打ち付けた。
「ダメ、そんなにしたら……声、出ちゃう……」
「出していいよ、ここはふたりだけの世界なんだから」
そして──フィニッシュ。
彼女は中出しを拒まなかった。
「本当に、大丈夫?」と俺が問うと、
「だって、今月もう生理きたし、今日は……したくてたまらなかったから」と笑った。
事後、ふたりでシャワーを浴びながら、志保さんはふと真顔になった。
「また、会ってくれる?」
その問いに、俺は何も言えなかった。
たぶん、そういう関係になるだろうとは思っていたが、ここまで早く関係が深まるとは。
「また、会いたいです」
俺の答えに、彼女は小さく頷いた。
【濡れた夜、満たされない心の奥底へ】
渋谷の街は、夜になると少し色を変える。
ネオンの光は輪郭をぼかし、人と人の境界を曖昧にする。まるで、そこに踏み込んでもいいのだと囁くように。
僕と結衣さんは、静かに歩いていた。
歩幅を合わせるように、気まずさもなく、自然に。
「ちょっと歩こうか」と彼女が言い出したのは、あのカフェを出た直後だった。
セックスレスの裏側にあった本音
「ねえ……さっきの話、変なふうに聞こえたかもしれないけど」
信号待ちの横で、彼女が口を開く。
「変じゃないですよ。むしろ……ちゃんと話してくれて嬉しかった」
そう応じると、彼女はふっと笑って、また前を向いた。
「5年、ずっと夫に触れられてないの。触れる気配もないし、こっちから求めても、何か…遠回しに断られる」
「理由、聞いたことあるんですか?」
「あるよ。でも、仕事が忙しいとか、疲れてるとか……ね。たぶんもう、私のこと女として見てないんだと思う」
その言葉に、僕は返す言葉を失った。
だけど、心の中にははっきりと浮かぶ言葉があった。
——それでも、僕はあなたを女として見てしまっている。
PCMAXでのLINE、そして即アポ
結衣さんとは、PCMAXで出会った。
掲示板の【大人の出会い】ジャンルで、彼女は控えめな一言だけを載せていた。
「家庭とは別に、人肌が恋しい夜があります。33歳、都内、主婦です。」
その一文が、やたらと胸に刺さった。
プロフィール写真も載っていない。でも、文章には妙にリアルな温度があった。
僕は、すぐにメッセージを送った。
「こんばんは。よければ少し、お話ししませんか?」
返事はすぐに来た。
その日のうちにLINEを交換し、やり取りは毎晩続いた。
相手のことを知るにつれて、気持ちが強くなる。
でも、そこに恋愛感情というよりも、「救われてほしい」という気持ちが先行していた。
ある夜、彼女がこう送ってきた。
「日曜の夜、少しだけ時間取れるかも。会ってくれる?」
あれが、即アポの始まりだった。
ホテルへの誘導、自然な流れで
「少し休もうか?」
僕の提案に、彼女は立ち止まり、小さく頷いた。
渋谷のホテル街の外れにある、比較的落ち着いたビジネスホテル。
「こういうの……初めてじゃない?」
「うん、初めて。掲示板も、あなたが初めてだった」
「緊張してる?」
「してる。でも、不思議と怖くないの」
チェックインの手続きを済ませて、部屋に入った瞬間、空気が変わった。
ホテルの灯りは薄暗く、部屋は静かだった。
まるで、この世界から少しだけ切り取られた、ふたりだけの空間のようだった。
ひとつのベッド、ふたつの温度
ソファに座ったまま、彼女は言葉を探すように口を開く。
「こんなふうになるって、思ってなかった。…でも、会ってからずっと、あなたの目が優しくて……ずっと嬉しかった」
「僕も。ずっと、触れたいと思ってました」
僕は彼女の手をそっと取り、指先に口づけをした。
震える手だった。緊張というより、覚悟の震えだった。
「…ねえ、キスしてくれる?」
彼女の唇にそっと触れた瞬間、ふたりの距離は一気にゼロになった。
キスは次第に深くなり、彼女の舌が甘く絡んできた。
「もう、我慢しなくていいよ……全部、任せるから」
下着の上から感じる体温、震える吐息。
ゆっくりと服を脱がせていくと、Cカップの乳房が柔らかく揺れた。
僕はその胸元に唇を落とし、ゆっくりと舐めた。
彼女は小さく声を漏らす。
「こんな……感じたの、久しぶり……」
指先を這わせて、太ももをなぞる。
ショーツの上からでも濡れているのが分かる。
「ここ、もう……濡れてるね」
「恥ずかしいけど……あなたに言われると、もっと濡れちゃう……」
そう囁いた瞬間、僕は彼女のショーツをそっと下ろした。
――昼下がりの背徳。消せない火種――
「今日は、平気なの?」
LINEの通知音とともに、彼女からの短いメッセージが届いたのは午前11時を少し回った頃だった。平日。俺は在宅ワークの日で、カメラもマイクも不要な資料整理のタスクに追われていた。
「平気。14時までは時間作れる」
そう返すと、数分と経たずに「会いたい」とだけ打たれたテキストが返ってくる。
その一言だけで、全身の血が一気に熱を帯びるのを感じる。
人妻である美沙子(仮名)とは、PCMAXで出会ってからもう3度目の逢瀬だった。
1度目はカフェ。2度目はホテル。3度目となる今日は、互いに「もう隠すものはない」という暗黙の了解のもと、初めから「体ありき」の密会だった。
場所は、駅から徒歩7分ほどの古びたビジネスホテル。
平日の昼間、ほとんど人通りのない裏道にひっそりと佇むその場所は、彼女のお気に入りでもあった。
「なんかね……また旦那に触れられそうになった」
エレベーターを上がってすぐ、部屋に入るや否や、彼女はそう呟いた。
淡いピンクのカーディガンに白いワンピース。一見して清楚そのものの格好だが、心の内側には火が灯っている。
「またって……?」
「うん、もう無理なのに。もう私、あなたでしか反応しないのに……」
彼女は俺の胸元に顔をうずめてきた。
その吐息が微かに震えている。手はすでにシャツのボタンへと忍び寄っていた。
◆人妻という存在に潜む業
人妻であるということ。
それは彼女にとって「既婚」という社会的立場であると同時に、「女を捨てる」選択を強いられてきた年月の重みでもあった。
旦那とは長年のセックスレス。
結婚10年目、子供はいない。夜の営みはもう何年も前からなく、会話も必要最低限。
そんな日々のなかで、美沙子が「女」として見られることは、家庭という名の牢獄の中ではすでに終わっていた。
「あなたに会ってから……毎日、自分が綺麗でいたいって思うようになったの。肌も、下着も、香りも……ねえ、嗅いで」
彼女は俺の首筋に顔を寄せ、自らの胸元に顔を引き寄せてくる。
香水ではない、自然な石鹸の香り。そして淡く漂う、発情した雌の匂い。
理性を壊すには、それだけで十分だった。
「もう我慢できない……して?」
甘えるように囁いた次の瞬間には、俺は彼女をベッドに押し倒していた。
◆昼のホテルで交わるふたり
ワンピースの下に身に着けていたのは、黒のレースの下着だった。
人妻がそれを選ぶ意味を、俺はもう理解していた。
「……見て、ほら、あなたのせいで、もう……」
彼女の指が自らのショーツの内側をなぞる。すでに湿っていた。
「奥まで……お願い……今日は激しくしていいよ……奥、いっぱいに当てて……っ」
腰を引き寄せ、俺のモノを導く彼女の手の動きには、もはや一切の戸惑いがない。
一突き目から、びくん、と背中をのけぞらせるほどの感度。
「イッちゃう……すぐ……すぐきちゃうの……中で……っ、お願い、中で感じたい……っ」
人妻の口から発せられるとは思えない言葉の数々に、俺は射精の衝動を必死に抑えながら、律動を深めていった。
フェラ、騎乗位、後背位。交わるたびに、「妻」ではなく「女」になっていく彼女。
それがまた、たまらなく背徳的で、興奮を煽ってくる。
◆セフレと恋人の境界線
行為が終わったあと、美沙子はベッドで裸のまま俺の肩に頭を預けていた。
「ねえ……私たちって、セフレ……だよね?」
その問いかけには、なぜか罪悪感と切なさが混ざり合っていた。
「うん。でも、それ以上でもあるよ」
俺がそう返すと、彼女は少しだけ安心したような笑みを浮かべた。
「セフレって、都合のいい関係っていうイメージあるけど……私にとっては、都合のいいどころか、唯一なの。あなたが……」
その言葉が全てだった。
もう引き返せない。
彼女は人妻でありながら、俺に心も身体も委ねている。
その事実が、俺の中で一種の所有欲と化していた。
◆終わらないLINE、続く密会
部屋を出たあとも、俺たちのやりとりは止まらなかった。
「今日もありがとう」
「身体、熱くてまだ震えてる」
「明日、またすぐに会いたい……」
まるで恋人のようなやりとり。だが、その裏には夫の存在という現実がある。
それでも美沙子は言った。
「次は……土曜日の昼、また同じ場所で待ってるね。旦那は実家に帰省するから」
背徳の扉は、音もなく開き続けている。
そして、そこに足を踏み入れるたび、彼女は「人妻」ではなく「俺の女」になっていくのだった。
——抗えない夜、求めあう身体。罪と快楽の交差点で
LINEのやり取りが終わった後、私はベッドの上でぼんやりと天井を見つめていた。彼女の名前は「真理子」。42歳、二人の子を持つ専業主婦。セックスレス歴7年、夫とはほぼ会話もなく、心も身体も離れていたという。そんな彼女と、出会い系サイト「PCMAX」で偶然マッチングしたのが3ヶ月前だった。
その夜、彼女から「今日は泊まっていかない?」というLINEが来た。私の中のタガが外れた。
◆ 禁断の一夜、ふたりだけの世界へ
午後9時過ぎ、私は真理子の家の近くまで車で向かった。駅から少し離れた閑静な住宅街。外観はどこにでもあるような一戸建てだが、その奥で私を待っている人妻がいると思うと、鼓動が高鳴った。
「おかえりなさい」
小さな声で玄関から出迎えた真理子は、ワンピース姿だった。ノーブラなのか、布越しに浮かぶ乳首の輪郭が微かに見える。その姿に、私はすでに理性を揺さぶられていた。
「ごめんね、こんな時間に…」
「ううん。来てくれて嬉しい…」
彼女の手が私の手を包む。その温度に、言葉以上のものを感じた。
◆ 熟れた人妻の本能、セフレという言葉では足りない関係
リビングで軽く缶チューハイを飲み交わしながら、会話は自然と深くなった。
「ねぇ、私って…ただのセフレ?」
唐突な質問だった。
「え?」
「このまま続けていいのか、たまに考えるの。私、誰かに必要とされたいだけなのかなって」
私は彼女の手を取り、そっと自分の胸に当てた。
「真理子さんは、俺にとって特別だよ。都合のいい関係で終わらせるつもりなんて、最初からなかった」
彼女の目に涙が浮かんだ。そのまま、ゆっくりと唇を重ねた。
◆ 脱ぎ捨てたのは服だけじゃない——羞恥、欲望、すべて
寝室のドアを閉めた瞬間、彼女は自らワンピースのボタンを外していった。薄暗い照明の中、白いレースの下着が浮かび上がる。ふっくらとしたEカップの胸、緩やかにくびれた腰、色気を帯びた身体は、年齢を重ねた女性特有の妖艶さに満ちていた。
「私…ほんとはこういうの、初めてじゃないの」
「え?」
「実はね、PCMAXに登録する前にも…何人かと…」
正直だった。だからこそ、愛おしいと感じた。経験豊富な彼女が、それでも私を選んでくれた。その事実が嬉しかった。
「だったら、今夜はその中で一番の夜にしよう」
そう耳元で囁きながら、下着の上から乳首を軽く指でなぞる。彼女の身体がピクリと反応する。
「だめ…すぐイッちゃいそう…」
「焦らないよ、今日は朝まで時間があるんだから」
ローターを取り出し、彼女の秘部に軽く当てる。小さな唸り声が漏れる。次第に下着は湿り、彼女の腰は自ら動き始めた。
「こんなの…恥ずかしい…でも…気持ちいいの…」
そのまま、ゆっくりと挿入した。
◆ 絡み合う吐息と汗、永遠に続くかのような快楽
彼女の中は驚くほど熱く、そして締め付けが強い。おそらく久々だったのだろう。最初の数分で、彼女はすでに2度ほど達していた。
「イクときは、中に出してもいい?」
「…赤ちゃん、欲しくなっちゃうかもよ?」
そんな冗談を交わしながら、ふたりは貪るように求め合った。後背位で突き上げながら、彼女の腰を掴む。時折、バックミラー越しに見えるような豊満な臀部が波打つ様子が脳裏に焼き付いた。
「もっと…奥まで突いて…っ」
「いくよ…!」
吐息を重ねながら、私は深く突き入れ、彼女の中で果てた。
◆ 行為後の静寂、でも心は確かに近づいた
明け方、彼女の隣で横になりながら、互いのぬくもりを感じていた。
「こんな夜、もう何年ぶりだろう…」
「また、来ていい?」
「もちろん。でも…私、本気になりそう」
その言葉に、私の胸も熱くなる。セフレという言葉ではもはや表現できない。確かに、彼女と私は「不倫」という罪の関係にある。だが、そこにあるのは、互いを求め、心と身体で確かめ合う“生”の感情だった。
◆ 交差する未来へ
彼女との関係は、今も続いている。PCMAXという出会いの場がなければ、こんな関係はなかった。でも、あの夜を経て、私はもう「ただの遊び」として彼女を見ることができない。
人妻、セックスレス、不倫、即アポ、羞恥プレイ、フェラ、セフレ、LINE交換、バイブ、ローター、カーセックス…。
数々のキーワードが、私と彼女の関係性を作り上げてきた。でも、ラベルでは語れない何かが、今の私たちを繋いでいる。
壊れてしまった境界線――人妻との禁断の関係、その果てに
深夜2時、LINEの通知音と共に
寝静まった部屋に鳴り響いたスマホの通知音。
「……起きてる?」
送り主は美咲――人妻でありながら、僕と何度も身体を重ねてきた女性だ。
僕は迷わず返信する。
「うん、起きてるよ。どうしたの?」
数秒後に既読がつき、すぐに返事が返ってくる。
「……今、旦那が出張でいないの。来れる?」
心臓がドクンと跳ねた。
背徳感と興奮。
彼女の家で、彼女のベッドで、夫の留守中に――。
僕はすぐに服を着替え、タクシーを呼んだ。
美咲の住む閑静な住宅街に到着する頃には、胸の高鳴りはピークに達していた。
静まり返った家の奥、灯る寝室の明かり
美咲の家に着くと、玄関のドアはすでに少しだけ開いていた。
ノブに手をかけると、カチリと静かに音を立てて扉が開く。
奥の寝室から、微かな灯りが漏れている。
恐る恐る足を進めると、そこには薄いネグリジェ姿の美咲が立っていた。
「……来てくれて、嬉しい」
彼女の声は、いつにも増して甘く、どこか切なさを帯びていた。
「……ほんとに、いいの?」
僕が小さな声で問いかけると、美咲は首を振って笑う。
「だめだって、わかってる。でも……あなたじゃないと、だめなの」
それは覚悟の言葉だった。
身体よりも、心が繋がってしまった夜
ベッドに座ると、美咲がそっと僕の隣に腰を下ろし、肩に頭を預けてくる。
「……なんだか、怖いの」
彼女の声が震えていた。
「このままじゃ、本当に壊れちゃいそうで」
僕は彼女の手を握りしめた。
「壊れたっていい。俺は、美咲のことが――好きだ」
それを聞いた瞬間、美咲の瞳から涙が溢れた。
そして、僕らは静かに唇を重ねた。
ただの欲望だけではない、心から求め合うような深いキスだった。
そのまま彼女をベッドに横たえ、何度も優しく身体を重ねた。
その夜は、いつもとは違った。
喘ぎ声や汗の匂いだけでなく、心の奥まで交わっていた。
朝焼けと、現実の足音
気がつくと、カーテンの隙間から朝焼けが差し込んでいた。
僕は裸のまま、美咲の横で目を覚ます。
彼女もすでに目を覚ましていて、窓の外を眺めていた。
「……朝だね」
「うん」
「現実に、戻らなきゃ」
そう言った美咲の横顔は、どこか寂しげだった。
もう、何度このセリフを聞いたことだろう。
「でも、また会ってくれる?」
僕が尋ねると、美咲は小さくうなずいた。
「……うん。でも、いつか終わらなきゃいけないとも思ってる」
終わり――それはずっと頭の片隅にあった言葉。
けれど、僕も彼女も、まだ踏み出せずにいた。
それでも止められない、ふたりの関係
あれから数日、美咲とは何事もなかったようにLINEでやりとりを続けていた。
「また会いたいな」
「……私も、そう思ってる」
気持ちは募るばかりだった。
LINE越しのやりとりでは、足りない。
声が聞きたい、肌に触れたい――。
そんな衝動が抑えられなくなった。
そして、また次の約束を取り付けた。
「来週の木曜日、旦那が飲み会で遅くなるの」
「了解。迎えに行くね」
背徳感は薄れ、むしろ「当たり前」のようになってしまった。
気がつけば、ただのセフレ関係を超えて、
僕は本気で彼女を愛してしまっていた。
ラストの夜が近づいている予感
次に会ったときの美咲は、どこか様子が違っていた。
抱き合った後、ベッドの上で彼女がポツリと呟いた。
「……もし私が離婚したら、あなたは私を迎えてくれる?」
「もちろんだよ。俺は本気で、美咲のことを――」
「ありがとう」
彼女はそれ以上何も言わなかったが、何かを決意した目をしていた。
「もしかして……別れる覚悟、してるの?」
「……ううん、まだ。でも、どこかでケリをつけなきゃって思ってるの」
僕は何も言えなかった。
この関係のゴールがどこにあるのか、もうわからなくなっていた。
そして、選ばれる未来とは――
一週間後、美咲からのLINEはなかった。
何度送っても既読はつかず、電話も繋がらなかった。
もしかして、すべてが終わったのかもしれない。
そう思いかけたその日の夜、ようやくメッセージが届いた。
「……今夜だけ、最後に会いたい」
その言葉を見た瞬間、僕は息を呑んだ。
ラストナイトになる予感――。
その夜、僕は再び美咲の家へと向かうことになる。