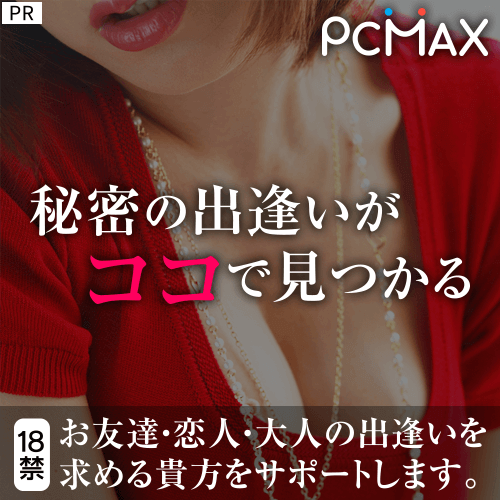― “主婦の仮面”を脱いだ日 ―
朝6時。夫と子どもを見送ったあと、私は台所でコーヒーを淹れながら、思った。
「今日も、誰にも見られないまま一日が終わるんだろうな」
洗濯機の音、子どもの弁当箱の匂い、無言の食卓。
愛情がないわけじゃない。だけど、“私”はどこに行った?
毎日、「お母さん」「奥さん」って呼ばれてるけど、
もう10年以上、「女」として触れられたことはない。
PCMAXを知ったのは偶然だった
ママ友グループLINEでの会話が発端だった。
「最近の女って、PCMAXとかやってるらしいよw」
「マッチングアプリのエロい版でしょ?やばw」
そのやりとりのスクショを見ながら、なぜか私は笑えなかった。
夜中、スマホを握りしめて、「PCMAX」で検索。
「会員登録はこちら」──興味本位のワンクリックだった。
初めてのログイン、そしてメッセージ
画面には、想像以上にたくさんの男性が表示された。
20代の若者もいれば、同年代の既婚者も。
「人妻」「寂しがり屋」「受け身希望」──
そんなタグを付けている女性も多くて、ホッとした。
自分のプロフをどう書くか迷った。
年齢、住んでる市、趣味──
「普段は主婦ですが、もう一度“女”として見られたいと思っています」
震える指で、そう入力した。
メッセージは思ったよりすぐ来た。
でもほとんどが「エロ目的」まる出しの軽い誘いだった。
やっぱり、やめようかな…と思った矢先、
1通だけ、違う空気のメッセージが届いた。
「真面目に話したいだけなんです」
その人は40代後半の会社員だった。
ハンドルネームは「匠さん」。
「家庭持ちですが、心が擦り切れてて。変な意味じゃなくて、ちゃんと話したくて」
そう書かれていた。
そこから、日々の生活、夫婦のすれ違い、
家で感じる“透明人間感”をポツポツと打ち明けた。
匠さんも同じだった。
「誰にも必要とされてない気がする」
「生きてる実感が、ない」
──この人と、会ってみたい。
約束の夜、そして“女”としての再会
待ち合わせ場所は、小さなカフェだった。
彼は優しげなスーツ姿で、やや緊張した面持ち。
私も、自分がこんなふうに“男と会う”ためにメイクをしたのは、
いったい何年ぶりだろう。
カフェでは他愛もない話をしたけれど、
空気は柔らかくて、苦しくなかった。
話の節々で「〇〇さんって、綺麗ですね」と言ってくれた。
褒められたのなんて、何年ぶりだろう。
帰り際、
「…もう少しだけ、一緒にいたいです」
と彼が言った。
私はうなずいて、ホテルへ向かった。
「知らなかった“熱”に、体が震えた夜」
■ あの夜、私は女に戻った
ホテルの扉が閉まったとき、私は一瞬、立ちすくんだ。
全身に緊張が走る。だけど、怖さよりも強かったのは「期待」だった。
匠さんは部屋に入るなり、すぐに照明を少し落とし、
「無理はしないでくださいね」と静かに言った。
彼の手が私の肩に触れた瞬間、
ずっと張っていた糸が、ぷつりと切れたように、涙がこぼれた。
「…すみません、こんな歳になって泣くなんて」
「いいんですよ。泣きたい時は泣いていいんです」
その言葉に、私は崩れるように彼に抱きついた。
■ 愛されるという感触
キスは、驚くほどやさしかった。
唇が触れ合うたび、心の奥底で凍っていたものが溶けていく。
その夜、私は「抱かれた」のではない。
「受け入れられた」「肯定された」──そんな感覚だった。
彼の手は、私の肌をなぞるたびに、何かを問いかけるようだった。
「あなたはここにいていいんですよ」
「あなたはまだ、美しいですよ」
ブラウスのボタンを外されるたびに、羞恥と快感が交互に押し寄せる。
「こんなに感じるなんて…」
耳元で自分の声が漏れて、驚いた。
■ 忘れていた「喘ぎ方」
私は、自分がどんな風に喘ぐのかを忘れていた。
セックスという行為そのものが、
長い間“義務”や“形式”に変わっていたからだ。
だけどその夜は違った。
ベッドに押し倒され、脚を割られた瞬間、
全身が粟立ち、声が漏れた。
「やっ…あっ……そんな…、だめ…」
でも、だめじゃなかった。もっと欲しかった。
匠さんの舌が胸元を這い、
乳首を含んだ瞬間、体が跳ねた。
「や…だめ……そこ……っ」
ひとつ、ひとつ、忘れていた快感が呼び覚まされる。
■ セックスのなかに、“感情”があった
その夜、彼は何度も私を抱いた。
でも、どの瞬間も「性欲」だけではなかった。
目を見て、名前を呼ばれ、
「気持ちいい?」と聞かれるたび、
まるで愛されているような錯覚を覚えた。
そして何より、自分の体が反応することに驚いた。
首筋に口づけられると、そこから熱が走り、
背中を這う指にゾクゾクとした電流が流れた。
挿入の瞬間──
あまりに久しぶりで、少し痛かった。
けれど、その痛みさえ愛おしくて、
「生きてる…」と実感した。
「すごく…、濡れてるね」
匠さんのその言葉に、羞恥と喜びが同時に溢れた。
■ 行為のあと、静かな余韻
セックスが終わったあと、彼は私を優しく抱きしめたまま、
しばらく何も言わなかった。
ベッドの中で聞こえるのは、互いの鼓動と呼吸だけ。
「…不思議ですね」
「なにが?」
「こんなに誰かに触れられたの、いつぶりだろうって」
「…俺もです」
体だけじゃなく、心まで満たされた気がした。
肌が触れているだけで安心するなんて、
どれだけ自分が飢えていたのか、思い知らされた。
■ 翌朝、家庭に戻って思ったこと
朝、家に帰った私は、いつものように台所に立っていた。
けれど、なにかが違った。
鏡に映る自分が、少しだけ「女の顔」をしていたのだ。
夫が新聞を読みながら「味噌汁、うまいな」と言った。
それだけで涙が出そうになった。
「ありがとう」って言葉が、ちゃんと口から出た。
子どもが「今日、友達と遊んでいい?」と聞いてきた。
「いいよ」と、自然に笑って言えた。
あの夜、私は“女”に戻った。
そして、家庭の中の「母」や「妻」としての役割に、
もう一度、自分から戻ることができた。
■ 匠さんとの関係、その後
それから何度か、匠さんとは会った。
でも、頻繁ではない。
むしろ、お互いに無理をしない距離感を保っている。
「次は、〇〇のカフェに行ってみたいですね」
「いいですね。じゃあまた、近いうちに」
そんなやり取りが、心の支えになっている。
セフレと言ってしまえばそれまでだけど、
これは「心のセックスフレンド」なのかもしれない。
そう思う。
「夜の余韻の中で、自分の欲望と向き合った私」
■ 心の震えと共に始まった余滴
あれから数週間、私は小さな余韻を抱えたまま日々を過ごしていた。
カフェで過ごした夜、共に過ごしたあの感触、匠さんの声のトーン。
それはまるで、柔らかい余韻が体中に残っているようだった。
でも同時に、自分の中に未解決の問いがあった。
「私は、あの夜、本当に“満たされた”のだろうか?」
「それとも、心の隙間を埋めただけにすぎないのだろうか?」
■ 不意に訪れた、別のメッセージ
PCMAXの通知の音に、私は驚いてスマホを手に取った。
それは匠さんからではなかった。
「彼には感謝してる。でも、私は他の可能性も見つけないと」──
そんな猜疑心も込めて、別の男性のメッセージを開いた。
「〇〇さんの経験談を読んで、共鳴しました。一緒にもっと“自分を知る時間”を過ごしませんか?」
その文面に、私は思わず考え込んだ。
「“自分を知る”って、どういうことだろう?」
その夜、また新たな岐路に立った予感がした。
■ 匠さんとの安心と、他の刺激の間で揺れる心
匠さんとの夜は、まるで安らぎのようだった。
心の暗部をそっと照らしてくれる温もりがあった。
でも、もうひとつ、芯から燃えるような“刺激”と“好奇心”も持ち合わせている自分がいることに気づいた。
「安心」だけでは満たされない。
でも、「刺激」だけでも疲れてしまう。
私は二つの感覚をバランスよく取り戻したいのかもしれない。
■ 新たなメッセージへの返信
メッセージをくれた男性(仮にKさんとしましょう)に、私はこう返した。
「メッセージありがとうございます。私も、“自分を知る時間”という言葉に惹かれました。
少しずつ、“信じられる刺激”を見つけていきたいと思っています。
まずは、一度お話してみませんか?」
送信後、少しの緊張と好奇心に包まれた。
自分を探求する旅のような、未知への第一歩だった。
■ 新たな出会い、軽やかな緊張感
Kさんは30代後半のフリーランス。
初対面のカフェでも、彼の言葉には“探究心”の匂いがあった。
「僕があなたのことを知るのも大事だけど、『あなたが自分をどう見つけたいか』を聞くのが楽しみなんです」
その言葉を聞いて、私は素直にこの人に心を開きたいと思った。
その夜は話すだけにして、距離を確かめるような会話で終わった。
でも、前とは違う種がこの夜、芽吹いた気がした。
■ “私ってこんな人かも…” 自己理解の深まり
その後、私は自分に問いかけるようになった。
-
私が本当に望むのは、誰かに安心されること?
-
それとも、自分の未知なる欲望に気づいてもらいたいこと?
-
どちらも欲しい自分を、どう肯定すればいいの?
匠さんとの関係に安心しつつ、Kさんとの関係に可能性を感じる。
この両方があっても、いいのではないかと思えるようになった。
■ PCMAXという場の特異性を実感した夜
PCMAXは「出会い系」ではなく、
「自分を再発見する場」でもあるのだと気づいた。
-
安心の夜も、
-
好奇心の夜も、
-
心の分岐点も、
すべて“自然に受け止めてくれる”、そんな場所。
私が迷っても、それを咎めない男たちがいる。
「“女としての境界線”が、静かにほどけた夜」
■ 二人の存在が、私を揺らす
匠さん──安心感と包容力をくれる人。
Kさん──未知への扉をそっと開いてくれた人。
ふたりはまるで、私の中の「理性」と「欲望」をそれぞれ代弁するような存在だった。
どちらかを選べば、どちらかを失う。
けれど、どちらも捨てきれなかった。
恋ではない。
でも、性だけでもない。
「女としての存在そのもの」を肯定してくれる、このバランスを私は崩したくなかった。
■ 匠さんからのLINE。「会いたいな」
その日、匠さんから短いメッセージが届いた。
「そろそろ、また会いたいな」
「何もしなくていい。ただ、あなたと一緒にいたいんだ」
思わず涙が出そうになった。
彼はいつも、私の気持ちの“先”にいてくれる。
でも、それは時に「守られすぎている」と感じることもあった。
■ 女として、少し“わがまま”になってみた
私は、匠さんに返信した。
「ありがとう。でも…少しだけ、私のわがままを聞いてくれる?」
「“女として”の私を、もっと欲しがってほしいの」
この言葉を打つ手は震えていた。
でも、言わなければ、いつまでも“守られる女”のままだったから。
■ そして再会した夜
静かな夜のカフェ。
匠さんは変わらず穏やかだったが、私の目を真っ直ぐ見てこう言った。
「わかったよ。
今日は、あなたが欲しいと言ったそのすべてに、応える日だ」
その言葉に、私は初めて“抱かれる準備”ができた気がした。
■ ホテルの部屋で、役割を脱ぎ捨てる
静かな照明の中、私はゆっくりとシャツを脱いだ。
匠さんも私を一切急かさず、ただ見つめていた。
ブラウスのボタンを外すとき、
彼がそっと手を添えてくれた。
「あなたのタイミングでいいよ」
その一言で、私は“受け身の女”を脱ぎ捨てた。
私は彼のシャツを脱がせ、ベルトに手を伸ばした。
「今日は、私があなたを求める番」
そう囁いた私に、彼は静かに微笑んだ。
■ 「女として」しか、伝えられない想い
重なり合った身体は、まるで「生き方」そのものをぶつけるようだった。
柔らかさと激しさ、リードと受動──
全てが交互に訪れ、混ざり合い、境界が消えていった。
行為のあと、私は彼に背中から抱かれたまま、こう呟いた。
「ありがとう。
今日の私を“女として”受け入れてくれて」
匠さんは優しくキスを落として、こう答えた。
「あなたは、ずっと前から魅力的だったよ。
でも今夜のあなたは、自分を信じていた。それが美しかった」
■ “Kさん”との関係の決着
数日後、Kさんから食事の誘いが届いた。
でも私は断った。
今の私は、誰かに“探究”されるより、
自分で自分を理解することに夢中だったから。
そして何より、匠さんの前では“自分を隠さなくていい”ということが、
今の私にとって何よりの安心だった。
■ 終わりじゃない。「始まり」が見えた気がした
シリーズ3の旅路は、
「寂しさ」から始まり、「出会い」によって開かれ、
そして「自分自身を女として受け入れる」ことで、
ようやくひとつの“章”が終わろうとしている。
でもこれは、終わりじゃない。
今の私はようやく、“始まりの入り口”に立ったばかり。
「“恋じゃない関係”の、その先へ」
■ 「セフレでも恋人でもない」、その曖昧な幸福
匠さんと過ごす時間は、静かで、心地よくて、どこか“永遠の一歩手前”にあるようだった。
肩書きもルールもない。だけど、信頼があって、身体のぬくもりがある。
それを“関係”と呼んでいいのなら、私はようやく自分の居場所を見つけたのかもしれない。
「誰かの妻でも、母でもない“私自身”として抱かれる喜び──」
この感覚をくれたのは、間違いなく匠さんだった。
■ 女友達の言葉が、心に引っかかった
そんなある日、学生時代の友人と久々にランチした。
彼女は言った。
「あなた、なんだか最近色っぽくなったよね」
「でもさ、結局“遊ばれてる”んじゃないの? そういうのって」
笑いながら言ったその一言が、胸に鋭く刺さった。
「遊ばれてる」──違う。そんなものじゃない。
でも、それを説明しようとした瞬間、自分の中にも一瞬だけ、迷いが生まれたのだった。
■ 自分の存在価値を問う夜
その晩、私はスマホ越しに匠さんの寝息を聞きながら、ふと考えてしまった。
「私は今、“何者”として彼と繋がってるんだろう」
「この関係に、終わりはあるのかな──」
恋人なら、嫉妬も独占も、ある程度は正当化される。
でも今の私は、何も要求できない。
なのに、心の奥では「他の女性と会ってほしくない」と願っていた。
その矛盾が、私をじわじわと苦しめていた。
■ もう一度、PCMAXを開いた理由
夜中、眠れずにベッドでスマホを開いた。
無意識に指が動き、PCMAXのアプリをタップしていた。
「こんな気持ちになるなら、いっそまた別の人と…」
でも、表示されたプロフィールたちを眺めても、心は微動だにしなかった。
Kさんにも、他の誰にも感じなかった“安心感”が、匠さんにはあるからだ。
私は気づいた。
「私が欲しかったのは、刺激じゃない。“理解される場所”だったんだ」
■ 「言葉にしないと、失う気がした」
数日後、匠さんとカフェで会った。
彼の目を見て、私は初めて“踏み込む”決意をした。
「ねえ、私たちって、何だと思う?」
「セフレ? 友達? 恋人…じゃないよね?」
匠さんは少し驚いた表情を見せたあと、真剣な目で言った。
「正直、名前はどうでもよかった。
でもあなたが不安になるなら、ちゃんと伝えるよ」
「僕にとって、君は“特別”だよ。
他の誰とも比べられない。
たとえ恋人って呼ばなくても、僕はずっと君といたいと思ってる」
その言葉を聞いた瞬間、私の中の霧がすっと晴れた。
■ 私はようやく、“自分を選べる”ようになった
“誰かに選ばれる女”になろうとして、
“いい母親”“いい妻”“いいオンナ”を演じてきた過去。
でも今は違う。
「私は、自分で“自分の人生”を選び始めている」
PCMAXというきっかけを通して、私は本当の意味で“自分を取り戻す”旅を始めた。